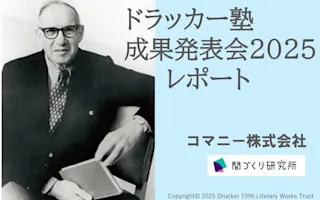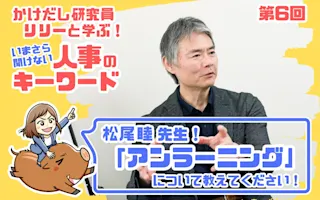人事図書館館長に聞く(後編)|自分たちが主役となり経営にインパクトを与える、人事のプロの8箇条
更新日:
- ダイヤモンドHRD総研

前編では、「人事のプロフェッショナル(以下、人事のプロ)」が求められる背景と、それを実現するための3つの心構えをお話いただきました。
① 実行部隊の認識を捨て、自分たちが課題設定する
② 現場と経営に肉薄し、自分軸で考え抜いて方向を示す
③ 成果にこだわり、周囲の人を動かす
吉田館長は、前編で紹介した3つの心構えに加え、残り5つを提唱し、これらを「人事のプロの8箇条」としてまとめています。後編では、より経営に資する成果につながる具体的な方法を5つ掘り下げていきます。前編と合わせてお読みください。
あわせて読みたい
4. 数値の裏側にある、経営者の想いを読み取る
前編に続きお話を伺っていきます。経営者はまず数値を見ますよね。そうしたアプローチで、経営に刺さる言葉で伝えることまでできるのでしょうか。
経営者の言葉の裏側にある想いを理解できるようになると、人事の取り組みも数字で示せるようになると思っているんです。例えば経営者が前年比売り上げ10%増を目指す時、例えばその業界の市場に対する発言力や社会的インパクト、持続可能性など、経営者だけが持つ、想いの裏付けが必ずあると思います。
そこを理解すると、商品なのか営業なのかなど、達成のために人事がサポートできる領域は変わってきますよね。商品はいいのに営業力が不足している、という状態だったとしたら、営業の領域に対してアプローチすると。
その際に採用・育成・制度といった人事が持つ選択肢から何を選ぶかはお任せください、いつまでにこのくらいの数値で成果を出します、と言えるようになる。経営者に対して、数字とアクションがつながった会話ができるようになると思うんです。
5. オペレーションのプロから課題設定のプロ
言葉の裏側にある想いまで理解することで数値とアクションをつなげることができるのですね。では、吉田館長がおっしゃる「人事のプロ」像には、経営にきちんと数値で示していけるような要素も含まれているのでしょうか。
細かく言うと、プロの定義は、時代や会社の状態によっても変わると思っています。人事におけるどんな人でも、新人でもベテランでも、まずは日々の業務のオペレーションのプロである必要があります。そこに習熟してはじめて、その先のルールそのものを考え直し、戦略そのものに関わる領域が担えるようになります。
その、ルールや戦略に関われるようになると、経営に数値で示せるプロに近いイメージでしょう。ただ、まずは、オペレーション、つまり実務への習熟がまずないと、その先の段階には進めません。
例えば一人しか人事部がいないような規模が小さい会社では、給与支払いとかトラブル対応だとか、日々のオペレーションだけで工数が奪われて、ルールや課題まで考えるような余裕が全くない、というよう状態がほとんどです。
だからこそ、オペレーション部分は少しでも効率化して、その先を考えられるような余白を作ることが、組織にとっても人事パーソン個人のキャリアとしても大事なことなんです。
ルールや戦略の領域に行くために、まずオペレーションの効率化が必要ということですね。
効率化の段階が終わったら、次の段階に行くというものではなくて、オペレーションの習熟はすべての段階の基盤なんですね。今、人事の仕事というのは膨大に膨れ上がっています。
例えば採用でも、昔は〇〇ナビに掲載すれば良かったのが、ダイレクトリクルーティングとかSNSとか、手段がたくさん出てきています。それに加えて、人事の領域って誰でも口が出せてしまうような側面があります。
例えばシステムの場合はまずCIOに相談してから進めるという段階を踏むような内容でも、人事に関してはストレートボールが多いように感じます。

6. 時には経営者の提案を、根拠を持って突っぱねる
ストレートボールです
「競合がSNS採用やってるみたいだから、ちょっとやってみたら」とか、気軽に口を出しやすいようなところがあると思いますね。一概には言い切れないですけど、経営者の方には「自分でできることを人事がちょっと劣化版でやっている」という感覚がある人が多い気がするんですよ。
「俺が採用をやればもっと作業できるし、制度も本気で考えればもっとうまくやれるんじゃないか」というような。
だからこそ、まず、手段については誰にも物を言わせないほど熟知した「Howのプロ」になることも必要だと思っています。
「Howのプロ」は、イメージしやすいですね。
現場を理解し、取り得る手段を熟知していれば、例えば経営者が何らかのアイディアを出してきた時に、なぜそれをしたいのかを良く聞いて、場合によっては「それはうちには必要ありません」と突っぱねたり、違う方法を提示したりすることができるようになるんです。
人事ができる、やるべき領域をしっかり定めていくことが、自社における人事の役割・目的を定めて行くことにつながって行くと思っています。
7. まず「Howのプロ」になる
人事図書館には「Howのプロ」になるための仕掛けもたくさん準備されていますね。
まずオペレーションを効率化しようと考えた時、給与ソフトや勤怠ソフト、タレントマネジメントソフトなど、人事が扱うツールは多岐に渡りますが、それらの検討にも膨大な時間がかかるんです。複数社に対して営業担当に連絡を取り、説明を受け、デモを見て、実際に動かしてみる、ということをしなければならない。
人事図書館に来れば、代表的なソフトを触って比較検討できますから、そうした時間と手間を節約できる。また、想像以上に盛り上がっているのが利用者間のSlack(チャットツール)です。
誰かが質問を投げると、驚くほど多くの人が意見をくれるんですね。もちろん会社名や企業固有の情報は伏せますが、例えばそうしたツールについて実際に使ってみた感想なんかも、かなり細かなところまで実際の利用者に聞くことができます。もちろんイベントに参加すれば、より具体的な生の声に触れることもできます。

Slack上でのコミュニケーションが、お互いの課題解決のヒントになることも多い。
なかなかここに来ることが難しい、一都三県以外の在住の方向けのオンラインプランもありますね。
首都圏だけでなく、地方にも届けていきたいという想いで設定したプランなんですが、オンラインには非常に価値があると言っていただくことがだんだんと増えてきています。(育児介護などの事情がある方は一都三県の方でもオンラインメンバー参加が可能です。)
つい最近、ある地方の市の方々が、複数社で視察に来られたんですね。その市全体で、東京に学ぼう、というような動きがあった上での視察の一環だったのですが、人事図書館を通じて首都圏と地方がつながっていく動きが見えてきたことは、とても嬉しく感じています。
8. 実際にはできない仕事を追体験する
首都圏と東京の違いもそうですが、企業規模の違いもありそうですね。今日お話いただいた人事のプロの話も、「大企業ならできるけれどうちでは難しい」と感じる中小企業の方もいるのではないでしょうか。
人事図書館にいらっしゃる方は、現実を変えたいだとか、自分のキャリアをもっと伸ばしたいなど、なんらかの問題意識を持っていらっしゃる方々です。そうした方々は、異なる状況に触れあえることを非常にポジティブに捉えてくださっています。
ご指摘のように、中小企業では一人が人事の仕事すべてを担っているような場合も少なくありません。そうした方が大企業の方とお話して、知らなかった手段や視点に気が付けた、というような声をお聞きします。
逆に大企業の方は人数がいる分、人事の中の自分の領域しか知らなかったりして、例えば採用専門でやってきた方が、労務の方の悩みや実態を知ることができる。こうした追体験が非常に重要だと思っているんです。
図書館の中では、例えば人事制度に困っている人がいたら、その話を聞きながら、そこにいる人で一緒に解決策を組み立ててみる、というような取り組みが自然に生まれてきます。
そうしたことをいくつか経験できれば、実際には経験できない仕事を追体験できる。その繰り返しで、自分だけ、自社だけでは経験できない領域に視野が広がって行くことで、社会全体に人事のプロを増やしていけるのではないかと考えています。
会社を超えて、働きやすい社会へ
人事図書館が人事の方々のハブとなっていけると、会社を超えて、社会全体の働きやすさが変わってくる可能性がありますね。
人事部という形に限らないとしても、会社や組織に「人事のプロ」が一人はいないと、今後組織が成立していかなくなるということを、最近感じているんですよね。これから労働人口が減り、採用はますます競争が激しくなる。
今まで一緒に働かなかったような方と一緒に働く必要も出てくるでしょう。それは外国人かもしれないし、今まで女性がいなかった職種における女性だったり、シニアの方や障害のある方だったりと、働く人の幅を広げなければ立ち行かない時代がやってきます。
かねてからチーム作り、組織作りは家族や恋愛の関係に似たところがあると思っています。誰も正式な教育を受けていないし、自分が体験したことしか分からない。先人たちは組織に関する書籍を山ほど残してくれているのに、いまだにみんな同じ石に躓いているんです。
社会課題解決を目的として立ち上げた組織の99%が、その手前の組織課題で崩壊すると聞いたことがあります。だったら組織課題を解決できたら、社会課題の解決はもっと進むんじゃないか。ちょっと大きい話をしてしまったかも知れませんが、
人事図書館が、そうした課題のお手伝いができれば、と考えています。

人事図書館 吉田館長の掲げる「人事のプロ8箇条」

お話を伺った方
人事図書館 館長 吉田洋介さん
立命館大学院政策科学研究科卒。卒業後、2007年リクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業立上、九州支社長、スクール事業責任者などを歴任。2021年3月株式会社Trustyyleを設立し、人事不在の企業を中心に組織作りの支援を行う。170名の有志と共にクラウドファンディングで472名から支援を受け2024年4月人事図書館を設立。これまで500社以上、スタートアップから大手企業まで幅広く、採用、人材育成、組織開発、人事制度策定などを経験。壺中人事塾では毎年30-40名ずつの参加者と共に人事の学びの場を磨き続けている。人事図書館ホームページはこちら。

株式会社ダイヤモンド社 人材開発編集部(ダイヤモンドHRD総研)
資料請求
サービスに関する説明資料を無料でお送り致します。
資料請求するお問い合わせ
人事課題に役立つメルマガ配信中
メルマガ読者限定で、ダイヤモンド社書籍のプレゼント企画、人事課題解決のノウハウ資料・セミナー、サービスの効果的な活用のヒント、などの情報をお届けします。(登録無料、登録情報はメールアドレスのみ、退会はいつでも可能)