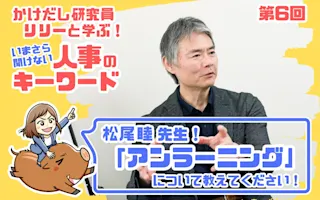内定者フォローの重要性を解説|内定辞退を防止するためのポイント
更新日:
- ダイヤモンドHRD総研

近年、多くの企業が採用活動に悩みを抱えており、中でも「内定辞退」は企業の成長戦略に影響しかねない課題です。そのため、ほとんどの企業が内定者フォローを実施しています。そんな中「果たして自社の施策は正しいのだろうか」と疑問を持っている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
学生が望んでいるフォローを実施しなければ、内定辞退を防ぐことはできません。本記事では、実際に企業が実施している施策や、学生がどのような内定者フォローを望んでいるかについて、アンケート結果をもとに詳しく解説します。貴社の内定辞退防止の参考にしていただければ幸いです。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
多くの企業が内定辞退に悩んでいる
冒頭で述べたとおり、企業の規模にかかわらず多くの企業が「内定辞退」を採用課題として挙げています。ここ数年、内定辞退者が「減った」企業よりも「増えた」企業のほうが多い状況が続いています。昨年と比較したのが下記のグラフです。

出典:ダイヤモンド就活ナビ就活意識調査(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース)
内定辞退が「かなり増えた」「やや増えた」と回答した企業は全体の31.9%で「やや減った」「かなり減った」の合計17.7%を大きく上回っています。規模別に見ても以下のような結果となりました。
- 従業員501名以上の企業:「増えた」30.7%「減った」24.3%
- 従業員500名以下の企業:「増えた」33.1%「減った」11.0%
以前は、大企業ほど内定辞退されにくいと言われていましたが、この結果からわかるように、大企業だから内定辞退が起こりにくいとは言えなくなってきているのが現状です。また、中小企業は母集団の形成においても、大企業に比べると集まりにくい傾向があります。これに加えて、内定辞退が増えれば企業経営への影響は避けられません。
なぜ内定者フォローが重要なのか
近年、内定者フォローの重要性が高まってきています。理由は、以前のように「内定=入社」の図式が成り立たなくなってきているからです。その背景には採用市場や就職活動の変化があります。内定者フォローの施策を実施する前に、まずは近年の変化を理解しておく必要があるでしょう。フォローが重要とされる主な理由は以下の3つです。
- 採用市場が変化しているから
- 内定後も就活を続ける学生が多いから
- 入社の主導権は学生にあるから
順番に解説します。
1.採用市場が変化しているから
新卒採用はここ数年、売り手市場が続いており、今後もこの傾向は続くと予想されています。実際に、2025年卒の内定獲得数は一人当たり平均3.15社で、2024年卒の2.94社から0.21社増加し、過去最多となりました。つまり「学生が企業を選ぶ側」にいるのです。

出典:ダイヤモンド就活ナビ就活意識調査(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース)
また、年々、就職活動の開始時期が早まっており、内定獲得の時期も早期化しています。2月以前に内定を獲得する学生が最も多く、入社までの期間が長くなるほど、フォローを怠ると気が変わりやすくなるのです。
2.内定後も就活を続ける学生が多いから
一人当たりの内定獲得数が平均3.15社という数字から、学生は複数社の内定企業の中から入社先を決めようとしていることが伺えます。つまり、自社が内定を出した後も、学生の就職活動は続いているのです。
一旦は内定を承諾しても、他に魅力的な企業から内定をもらえれば、その企業に流れる可能性は十分あり得ます。そのためにも、定期的なフォローは欠かせません。
3.入社の主導権は学生にあるから
売り手市場では、学生側に入社の主導権があります。学生は複数社から内定を獲得し、企業の対応やコミュニケーションの質などを総合的に判断して、入社する企業を決められる立場です。少しでも納得いかない部分があれば、他社へ心変わりする可能性があります。
「内定を出したから大丈夫だろう」とフォローを怠ると、学生は不安になり「この会社でいいのか」と思うようになります。このような心理状況になれば、入社したい気持ちが薄れていくのです。
なぜ学生は内定を辞退するのか
内定を辞退する学生には、必ず理由があります。新卒学生は社会人経験がないため、仕事に就く不安に加えて、今までの環境が変わる不安が大きいのです。内定辞退を防ぐためには、こうした心理状態を踏まえたフォローが必要です。学生が内定を辞退する理由には以下のようなものがあります。
- 社会人になる不安
- 仕事についていけるのか不安
- 社風や人間関係が不安
- 待遇や労働環境に関する不安
- 会社の経営に対する不安
企業が想像している以上に、学生は不安を抱いています。場合によっては個別相談を実施するなど、ひとつずつ不安を解消させる必要があるでしょう。
社会人になる不安
社会人生活にうまく適応できるか不安に思う学生は少なくありません。とくに、規則正しいな生活や毎日の通勤、社会人としての心構えなど「自分にできるのだろうか」といった、環境の変化に対する不安を抱えています。
こうした不安が内定辞退に直接つながるわけではありませんが、他の原因と重なって「内定辞退」の決断を後押しするのです。そのため、内定フォローでは社会人になる不安やプレッシャーを、いかに和らげられるかが重要となります。不安を解消する方法としては、年齢の近い若手社員の経験談を聞いてもらうのも効果的です。
仕事についていけるのか不安
学生は初めて企業で働くため「どのような仕事を任されるのか」や「仕事についていけるのか」と不安になります。とくに、専門職や結果が求められる営業職などは、より不安が大きくなるでしょう。こうした不安を軽減するためには、事前研修が効果的です。
実際に業務を担当している社員の話や、事前研修で基礎知識を習得してもらうなどがよく実施されます。また、入社後も研修でしっかり学べることも説明しておくと不安が和らぐでしょう。
社風や人間関係が不安
社風や人間関係に対する不安も内定辞退の理由のひとつです。多くの学生は、面接で顔を合わせる人事担当者としか面識がないため、職場の雰囲気や人間関係に不安を感じやすくなります。こうした不安を解消するためには、社員との交流会や職場体験が効果的です。また、実際に業務中のオフィス見学や、個別に相談できる機会を作るのも不安解消につながります。
待遇や労働環境に関する不安
複数の内定をもらってから、改めて給与や労働時間などの条件面を比較する学生も少なくありません。他社と比較して条件が悪かったり、労働時間や手当などが明確になっていなかったりすると「ブラックなのではないか」といった不安が芽生えます。
労働環境については学生から質問しづらい項目のため、企業説明会でおおよその残業時間を説明するなど、誤解や不安が生じないようにしておく必要があるでしょう。
会社の経営に対する不安
就職活動中はほとんどの学生が、業界や仕事内容に注目します。しかし、内定後に改めて入社するかどうかを決断する際に、将来性や安定性を気にする学生も少なくありません。とくに近年は、保護者が内定先の企業に対し「経営状況は大丈夫か」と問い合わせるケースも増えています。
質問に対して納得のいく回答が得られなければ不安が大きくなり、結果的に保護者から入社を反対され、内定辞退の申し出があることも少なくありません。このような事態を避けるために、保護者向けに説明会の開催や社内報を送付している企業もあります。
学生が内定先企業に期待しているフォロー
内定者フォローは辞退防止に有効な手法ですが、企業側と学生側の思惑が一致していなければ効果は得られません。学生は企業の内定者フォローに何を期待しているのでしょうか?アンケートの結果、もっとも多かった回答を紹介します。
1位:定期的に連絡がほしい(54.7%)
2位:内定者同士で連絡を取りたい(51.3%)
3位:先輩社員の話が聞きたい(48.5%)
4位:懇親会の開催(47.6%)
5位:仕事に役立つスキルを身につけておきたい(35.6%)
学生が望んでいるフォローを理解すれば、辞退防止対策のヒントが見えてきます。

出典:ダイヤモンド就活ナビ就活意識調査(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース)
1位:定期的な連絡
定期的な連絡を望んでいる学生は全体の54.7%に上り、内定者フォローにおいて定期的な連絡は必須と言えるでしょう。昨年も50.5%の学生が「定期的に連絡が欲しい」と回答しており、半数以上の学生が企業からの連絡が途絶えると不安だと感じています。
連絡手段としては、メールやチャット、電話などが一般的ですが、最近ではSNSを活用する企業も増えています。入社まで一度も顔を合わせないのはよくありません。月に1回くらいは連絡し、困り事や不安はないか確認したり、事前研修を実施したりすると良いでしょう。
2位:内定者同士のつながり
内定者同士でのコミュニケーションを求めている学生が51.3%と半数を超えています。昨年も58.0%が「内定者同士で連絡を取りたい」と回答していることからも、横のつながりを求めていると言えるでしょう。同期とのつながりは入社後の悩みや不安を相談できるだけでなく、良きライバルとして刺激しあう関係も築けます
入社前に内定者同士の連帯感を強めておけば、企業への帰属意識も向上し、入社への期待を高めることが可能です。また、理解できる仲間がいれば、内定辞退や早期退職の防止にもつながります。そのため、内定者同士で交流できる機会を増やし、自然なコミュニケーションをとりやすくするのがポイントです。
オンライン交流会やグループチャットなどを利用すると、遠方の学生も参加しやすいでしょう。こうした企業側の配慮も必要です
3位:先輩社員へのヒアリング
「先輩の話を聞きたい」との意見も48.5%と高く、実際に現場で働いている社員と話をしたいと考えています。昨年も47.9%と、ほぼ変わらない結果であることからも、先輩社員と交流できる機会は内定フォローにおいて必須と言えるでしょう。
先輩社員は、入社2、3年目の若手社員が適任です。学生に年齢の近い社員のほうが親近感を感じ、話しやすくなります。また、同じ部署になる予定の社員や、出身大学が同じ社員の話も共感しやすく効果的です。
4位:懇親会の開催
内定者フォローの中でも懇親会の開催は、最も一般的な施策のひとつです。カジュアルな雰囲気の中で、社員や他の内定者と気軽に話ができるため、打ち解けやすくなります。実際に47.6%の学生が、懇親会の開催を期待すると回答しており、有効な手段と言えるでしょう。
食事をしながらの懇親会だけでなく、ゲームやスポーツなど、できるだけ緊張感の少ないイベントを絡めた懇親会にするとさらに効果的です。
5位:仕事に役立つスキルの習得
入社までの期間を、スキルを習得する時間に充てたいと考えている学生も少なくありません。実際に、35.6%の学生が「仕事に役立つスキルを身につけておきたい」と回答しています。「少しでも早く戦力になりたい」という前向きな気持ちの現れです。このようなニーズもあるため、入社までに課題を与えても良いでしょう。
方法としては、経営者が出版した書籍を与えたり、オンライン教材などが一般的です。このような教材は、自分のペースで学習できるため負担になりません。また、事前にスキルを習得してもらえば、入社後の研修がスムーズになるメリットもあります。
内定辞退を防ぐための施策|フォローの事例
実際に、企業がどのような内定フォローをしているのか気になる方もいるでしょう。ここでは、実際に企業が行った、あるいは今後予定している施策の上位5つを紹介します。
- 内定者懇親会
- 採用担当者との個人面談
- 先輩社員訪問・懇談
- 内定者研修
- 職場見学会
自社の施策を考える参考にしてみてください。

出典:ダイヤモンド就活ナビ就活意識調査(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース)
内定者懇親会
企業が実施した内定者フォローで、一番多かったのは内定者懇親会です。以前から使われている一般的な手法で、501名以上の企業で79.0%、500名以下の企業でも77.1%の企業が実施しています。学生に対するアンケート結果でも、約半数の47.6%が懇親会の開催を望んでおり、有効な手段と言えるでしょう。
懇親会のメリットは、社員と学生が同時に同じ会場で顔を合わせられるため、効率よくコミュニケーションが取れる点です。一方、同僚や社員との相性や社風が合わないと感じて、内定を辞退されるケースもあります。また、強制的に参加させることもイメージダウンにつながるため、注意が必要です。
採用担当者との個人面談
採用担当者との個人面談は、一人ひとりの不安や疑問に対応できる貴重な機会のため、実施している企業が多いです。501名以上の企業では67.3%、500名以下の企業でも50.0%が実施しています。一方、学生も30.6%が個別面談を望んでおり、大勢の前では言いにくい相談をする機会がほしいと感じているのです。
また、個人面談では、一人ひとりの入社意欲を把握できるため、入社意欲の低い学生を重点的にフォローするなどの対策が講じやすくなるメリットがあります。
先輩社員訪問・懇談
先輩社員を訪問してリアルな話を聞く手法は、以前から多くの企業で実施されています。先輩社員訪問・懇談を実施している企業の割合は501名以上の企業で65.9%、500名以下の企業でも46.7%と高めです。先輩社員からの詳しい話を聞けば、より納得できるため、早期退職を防止する効果があります。
先輩社員の話は信頼性が高く、説明会では聞けなかった話も聞ける可能性があるため、学生にとってもメリットがあるでしょう。実際に、学生も48.5%が「先輩社員の話を聞きたい」と回答しており、内定辞退の防止に効果が期待できます。
内定者研修
内定者研修も一般的によく実施される手法です。入社前に業務に必要なスキルを習得し、入社後の業務をスムーズに行えるようにする目的があります。研修では、ビジネスマナーや業界知識、社内システムの使用方法などを習得するのが一般的です。
内定者研修は、501名以上の企業で31.8%、500名以下の企業では39.5%が実施しており、学生も29.0%が実施して欲しいと望んでいます。
職場見学会
職場見学会は、実際の環境や業務の流れを把握できる点がメリットです。501名以上の企業では29.0%、500名以下の企業でも23.8%が実施しています。
実際に自分の目で確認すればイメージが湧きやすく、入社への意欲を高める効果があるため、企業ではよく用いられる手法です。また、職場の雰囲気や社風などを肌で感じることができ、ミスマッチを防ぐ効果もあります。従って、何らかの形で、実際の職場を見てもらう機会は作ったほうが良いでしょう。
対面での内定者フォローが内定辞退のカギを握っている
近年はオンライン化が進み、Web上で面談や交流会を実施する企業も増えています。オンライン化によって、コストの削減や移動時間を効率化できる点は、学生、企業どちらにとってもメリットです。一方で、対面で接触する機会は以前に比べて減っています。

出典:ダイヤモンド就活ナビ就活意識調査(株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース)
直接会って話したほうが不安解消につながりやすいこともあり、多くの学生が対面の重要性を感じています。調査結果で、75.7%の学生が「対面」での交流を希望している現状から見ても明らかです。この流れは昨年から変わっていません。
実際に企業が実施した内定者フォローの事例
ある企業では、アンケートでも回答の多かった「内定者同士の横のつながりを深める」ことが内定者フォローの課題でした。月に1回、オリエンテーションや研修、個別面談などを実施しています。しかし、指導する側と学生では価値観が異なり、一方通行の研修になりがちでした。
そこで、Z世代の学生が開発にかかわった「Z世代のための内定者フォローワークショップ」『ツナマル』を導入しています。実際に『ツナマル』を利用して、内定後の早い段階で対面を3回、オンラインで1回の研修を実施した結果、内定者同士の交流が深まり人事部門との距離も縮まりました。これをきっかけに、その後のイベントにも積極的に参加する姿勢が見られています。
この事例のように、こうした対策教材を活用するのも、効果的な内定フォローの手段として有効です。
まとめ
多くの企業が内定辞退を防ぐための施策として「内定者フォロー」を実施しています。内定者フォローは学生の不安を軽減し、企業への信頼感や帰属意識を高める有効な手段です。一般的には、定期的な連絡や社員との意見交換、懇親会の開催などが多く実施されています。
また、学生の希望と企業側が実施した内容を比較しても、内定者フォローに関して両者に大きな認識のズレは見られません。両者とも人を通じてのフォローを重視しています。内定者フォローを成功させるためのポイントは、一人ひとりの不安を解消するためのきめ細やかな対応と、企業の魅力や将来性を効果的に伝えることです。
さらに、オンラインではなく対面での交流も欠かせません。単にコミュニケーションをとるだけでなく、いかに内定者に寄り添えるかが辞退防止の鍵となります。

記事監修
株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース 経営企画室 室長 高村 太朗
1998年、株式会社ダイヤモンド・ビッグ社入社。法人営業として、首都圏と大阪で大手企業を中心に新卒採用支援や人材開発支援を担当。「ダイヤモンド就活ナビ」編集長、営業企画室長を経て、現職。「ダイヤモンド就職人気企業ランキング」「採用・就職活動の総括」をはじめ、新卒採用マーケットに関する調査・分析に携わっている。

株式会社ダイヤモンド社 人材開発編集部(ダイヤモンドHRD総研)
資料請求
サービスに関する説明資料を無料でお送り致します。
資料請求するお問い合わせ
人事課題に役立つメルマガ配信中
メルマガ読者限定で、ダイヤモンド社書籍のプレゼント企画、人事課題解決のノウハウ資料・セミナー、サービスの効果的な活用のヒント、などの情報をお届けします。(登録無料、登録情報はメールアドレスのみ、退会はいつでも可能)